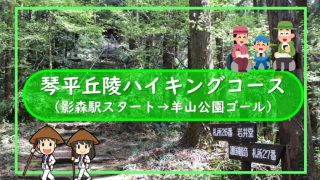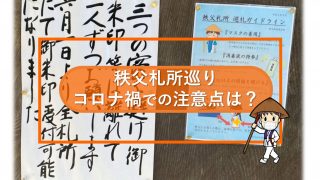⚔『鬼滅の刃』の聖地に行きたい!
⚔秩父は『鬼滅の刃』の聖地なの?
⚔『鬼滅の刃』の世界観にどっぷり浸かりたい!
この記事は、そんな方に向けて書いています。
埼玉県・秩父エリアには、『鬼滅の刃』との関連性を感じるスポットが点在しています。2025年7月の“無限城編”公開により再び過熱している鬼滅ブームによって、聖地としての秩父にも再び注目が集まっています。
-でも、そもそも、秩父って『鬼滅の刃』の聖地なの?
はじめに結論を記すと、秩父を“鬼滅の聖地”とまで断言することは出来ません。しかし
作品の舞台となっている大正時代は、秩父が大きく発展していった時代であり、秩父には現在もその時代の面影を感じることができるスポットがあります。また、秩父には公式が認めるスポットもあるため、秩父と作品の関連性は大いにあると言っても過言ではありません。
そこでこの記事では、埼玉県・秩父エリアにある『鬼滅の刃』の世界観を感じる事ができるスポットを一挙紹介していきます。この記事を最後まで読んでいただくことで、鬼滅ファンなら秩父という町に興味を持つこと間違いなし!
秩父札所巡りのお先達であり、鬼滅ファンでもある当サイト管理人ならではの視点で解説します!
\ 鬼滅の刃 無限城編 キャンペーン中/
目次
竈門兄妹の出身地「雲取山」
 (画像:夜明けの雲取山山頂標と富士山)
(画像:夜明けの雲取山山頂標と富士山)
『鬼滅の刃』の物語は、竈門炭治郎と禰豆子が雪山で静かに暮らす日常から始まります。
その冒頭シーンの舞台として、公式ファンブックでも“出身地”と明記されているのが、雲取山(くもとりやま)です。
雲取山は、東京都・埼玉県・山梨県の県境にまたがる日本百名山のひとつで、標高は2,017メートル。関東地方の最高峰でもあります。登山道は複数あり、秩父・三峰神社側から登る「三峯神社コース」は、片道約5〜6時間、往復では10〜12時間かかるため、登山初心者には難易度が高いコースです。
熊の目撃情報も多発し、“おすすめスポット”と気軽に紹介するのがためらわれるほど、山そのものの厳しさが魅力でもあります。(作品中においても、炭治郎のお父さん・炭十郎が、大熊を一人で倒すシーンが印象的でしたね)
しかし、そんな険しい道中にこそ、作品とリンクする発見もあります。たとえば、三峰ルート途中には「炭窯跡」があり、炭治郎の家業である“炭焼き”の文化が、この地域でも根付いていたことがわかります。また、三峯神社のビジターセンターでは『鬼滅の刃』に関連した紹介もされており、作品と山の結びつきが感じられる仕掛けも見逃せません。
 (☞鬼滅の刃 1巻)
(☞鬼滅の刃 1巻)
雲取山は、アクセスのしやすい“映えスポット”ではありません。しかし、その厳しさと自然の豊かさ、そして時代背景の重なりが、竈門兄妹の生きた世界をよりリアルに想像させてくれます。簡単に行ける場所ではないからこそ、そこがまた聖地としての価値・作品の価値を高めてくれているような気もします。
ちなみに、雲取山の登山道入口がある三峰神社までは、西武秩父駅から直通バスが出ています。三峰神社までバスで行き、参拝がてら雲取山の登山道入口まで行って、その雰囲気を味わってみるのもいいかもしれません。ただし、直通バスも西武秩父駅から片道だけで約1時間30分かかります。
三峰神社へのアクセス情報

| 住所 | 埼玉県秩父市三峰298-1 |
|---|---|
| アクセス | ・西武鉄道「西武秩父」駅から西武バスで約90分。 ・秩父鉄道「三峰口」駅から西武バスで約60分。 |
“竈門“に“柱“…どう考えても鬼滅!?竈三柱神社
 (画像:秩父大滝にある「竈三柱神社」)
(画像:秩父大滝にある「竈三柱神社」)
鬼滅ファンなら「竈三柱神社(かまどみはしら)」という名前を見てドキッとするかもしれません。
神社名に「竈(門)」と「三柱」という言葉が含まれており、「竈門」は主人公・竈門炭治郎の名字、「柱(はしら)」は作中で鬼殺隊の最高位の剣士たちを指すものです。しかも、この竈三柱神社は、竈門兄妹の出身地である雲取山(三峯神社)への登山道の近くに位置していることもあり、その関係を疑わずにはいられません。
ただし、この神社は公式に作品の聖地として認定された場所ではなく、偶然の一致に過ぎません。それでも、全国に数多くある「竈門神社」の中で、名前に「柱」まで含む神社はとても珍しい存在です。また、“三柱”とは誰だろう?無惨を倒したあと一緒に暮らした炭治郎と善逸と伊之介の3人のこと?…なんていう妄想までしてしまうファンの人もいるのではないでしょうか。
 (☞鬼滅の刃 片羽の蝶 )
(☞鬼滅の刃 片羽の蝶 )
この竈三柱神社は、火事除けの神様を祀っている神社で、山あいの静かな地域に佇んでいます。アクセスは不便な場所にありますが、その分ひっそりとした雰囲気が漂い、古くから地域の人々に信仰されてきた由緒ある神社でもあります。こうした名前の偶然が生むファンの想像力も相まって、竈門三柱神社は「もしかしたら…?」というロマンを感じさせてくれる魅力的なスポットです。
竈三柱神社へのアクセス情報

| 住所 | 秩父市大滝696 |
|---|---|
| アクセス | 秩父鉄道「三峰口」駅より、バス(三峰口線小双里行)で「下大輪」下車(11分)。そこから徒歩3分。※本数が少ないため、事前によく調べる必要があります。 |
大正時代、女性の間でブームとなった「秩父銘仙」
 (画像:ちちぶ銘仙館)
(画像:ちちぶ銘仙館)
『鬼滅の刃』の舞台は、大正時代。作品内では、禰󠄀豆子はもちろん、鬼の珠世(たまよ)・沼鬼に襲われた女性たち・浅草の女性たちなど、当時の着物を身にまとった女性が多く登場します。その背景として注目したいのが、「秩父銘仙(ちちぶめいせん)」と呼ばれる絹織物の存在です。
秩父銘仙は、大正時代に全国的な人気を誇ったモダンな着物。大胆な柄、鮮やかな色彩、そして日常着としての実用性から、多くの女性たちに愛されました。アニメの中で見られる女性たちの衣装や雰囲気も、どこかこの銘仙に通じるものがあり、『鬼滅の刃』の時代を肌で感じられる一つの手がかりになるかもしれません。
そもそも秩父は、古くから養蚕や繊維業が盛んな土地でした。1914年(大正3年)には秩父鉄道が秩父駅まで開通し、物流と産業が一気に発展。さらに1923年(大正12年)には渋沢栄一の従兄・諸井恒平が関わった「秩父セメント」も設立され、林業・鉱業も含めた重工業地帯へと成長していきます。これにより秩父の人口は急増し、戦後には3万人を超えるほどになりました。ちなみに、秩父のセメントは、関東大震災からの復興、戦後の東京復興、新幹線基盤など高度経済成長期の首都圏のインフラ整備も支えてきました。
秩父の銘仙は、まさにそうした時代の女性たちの「おしゃれ」と「生き方」の象徴とも言える存在です。現在では、秩父市内に銘仙の展示施設である「秩父銘仙館」があり、当時の生地を実際に目にしたり、試着したりすることも可能です。『鬼滅の刃』の世界観に触れたい方にとって、単なる“聖地”ではない、時代背景や生活文化を体感できるこの「秩父銘仙」は、見逃せない要素の一つです。
ちちぶ銘仙館へのアクセス情報

| 住所 | 埼玉県秩父市熊木町28-1 |
|---|---|
| アクセス | 西武秩父駅から徒歩5分 |
| 館時間開 | 午前9時~午後4時 |
| 休館日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 公式HP | https://www.meisenkan.com/ |
炭治郎が修行で切った大岩!?
 (画像:秩父小鹿野版・炭治郎が斬った大岩…似てる!?)
(画像:秩父小鹿野版・炭治郎が斬った大岩…似てる!?)
『鬼滅の刃』の序盤で特に印象的だったのが、炭治郎が修行の果てに斬った大岩のシーン。そんな「あの大岩」に似ているとSNSで話題になったスポットが、埼玉県秩父郡小鹿野町にあります。アニメの岩そのものではないにせよ、「あの場面みたい!」と感じるファンが少なくないようで、実際にコスプレで訪れたという報告も見られます。
 (☞鬼滅の刃 フィギュア 絆ノ装 弐拾ノ型 全2種セット 真菰 & 錆兎)
(☞鬼滅の刃 フィギュア 絆ノ装 弐拾ノ型 全2種セット 真菰 & 錆兎)
ただし、この岩は公式に認定された“聖地”ではありません。ちなみに、奈良県の「柳生一刀石」も“炭治郎の大岩”として有名ですが、こちらも公式とは無関係。あらためてアニメと見比べると…実はどちらもそこまで似てない、というのが正直なところです(笑)。
それでも、少しでも作品の世界観に近づきたいというのがファン心というもの。実際、筆者である私もこの小鹿野の岩を訪れました。その時の様子は別記事「☞【秩父小鹿野版】鬼滅の刃・竃門炭治郎が切った“大岩“への行き方」でも紹介していますので、よければあわせてご覧ください。
この大岩は、市街地からはやや離れた場所にあり、気軽に立ち寄れるスポットではありません。しかし、すぐ近くには秩父札所31番・観音院という歴史あるお寺がありますので、大岩とセットでの訪問がおすすめです。観音院の荘厳でありながら静寂を感じる境内もまた、作品に通じる世界観を感じさせてくれますよ。
【秩父・小鹿野版】炭治郎が斬った大岩へのアクセス情報
 (画像は、秩父札所31番・観音院。ここから徒歩5分の場所に、大岩がある)
(画像は、秩父札所31番・観音院。ここから徒歩5分の場所に、大岩がある)
| 住所 | 〒368-0111 埼玉県秩父郡小鹿野町飯田 |
|---|---|
| アクセス | 西武秩父駅より、西武秩父駅から西武バス・栗尾行き「栗尾」で下車(約50分)。→さらに、「栗尾」から徒歩で秩父札所31番・観音院の山門付近にある駐車場へ(約45分)→さらに徒歩5分 |
| 関連記事 | ☞【秩父小鹿野版】鬼滅の刃・竃門炭治郎が切った“大岩“への行き方 |
あのSLは無限列車?蒸気機関車の通る町
 (画像:秩父鉄道公式HPより)
(画像:秩父鉄道公式HPより)
『鬼滅の刃』の「無限列車編」と言えば、蒸気機関車(SL)の走る闇夜のシーンと、車内で繰り広げられる壮絶な戦いが強く印象に残ります。秩父でもSLが走っていると知って、「もしかして無限列車のモデルでは?」と感じた方もいるかもしれません。ですが、実際には、秩父鉄道のSL「パレオエクスプレス」はモデルではありません。
無限列車のモデルとされているのは、国鉄8620形蒸気機関車。1914年に日本初の量産型として製造され、大正時代の鉄道の象徴とも言える存在です。現在、保存されている車両は九州・肥薩本線の「SL人吉(58654号)」と、京都鉄道博物館に展示されている「8630号」の2両のみとされています。作中で描かれた無限列車の死闘の時期は、大正5年(1916年)11月18日頃というマニアによる考察もあり、実際の歴史背景ともしっかりリンクしています。
 (☞【国内盤DVD】【新品】【PG12】劇場版 鬼滅の刃 無限列車編)
(☞【国内盤DVD】【新品】【PG12】劇場版 鬼滅の刃 無限列車編)
一方、秩父鉄道の「パレオエクスプレス」は、熊谷〜三峰口間を中心に運行されており、週末や長期休暇中には多くの鉄道ファンや観光客を魅了しています。車窓から見える山々の風景やレトロな駅舎の佇まいは、どこか大正ロマンを感じさせてくれます。SLの黒煙を上げながら走る姿を間近に見れば、無限列車を思い出さずにはいられません。
神楽が伝承される信仰の町
 (画像:横瀬町里宮の神楽@武甲山御嶽神社)
(画像:横瀬町里宮の神楽@武甲山御嶽神社)
『鬼滅の刃』の中で重要な意味を持つ「ヒノカミ神楽」。炭治郎が受け継ぐ舞は、鬼を祓い、亡き者を想い、命を繋ぐ“祈り”そのものです。実は、秩父もまた、神楽をはじめとする「祈りの文化」が色濃く残る地域。この土地に根付く精神性は、まさに鬼滅の世界観とどこか重なり合うものがあります。
秩父地方には20ヵ所以上で神楽が伝承されており、獅子舞や歌舞伎とともに、地域の文化として大切に守られています。中でも、秩父の代表的な神楽といえば「秩父神社神楽」。この神楽は全35座から成り、能や歌舞伎の手法を取り入れた演劇的な構成が特徴です。関東一円に広がる江戸神楽とは異なり、独自の芸統を持ち、静かな中にも神聖な力強さを感じさせてくれます。特に、12/2・3に行われる「秩父夜祭」では、豪華な屋台と共に披露される神楽の舞が圧巻で、国の重要無形民俗文化財にも指定されているほどです。
 (☞【限定販売】鬼滅の刃 竈門炭治郎 ヒノカミ神楽 円舞 完成品フィギュア)
(☞【限定販売】鬼滅の刃 竈門炭治郎 ヒノカミ神楽 円舞 完成品フィギュア)
また、秩父地域では年間300以上もの祭りが執り行われており、信仰と祭礼が今も生活の中に息づいていることがわかります。これらの伝統文化の背景には、先人たちの「祈り」や「願い」があります。鬼と人、命と死、過去と未来…そんなテーマを描いた『鬼滅の刃』の根底にある価値観と、秩父の文化が静かに重なり合う瞬間を、ぜひ現地で感じてみてください。
\ 鬼滅の刃 無限城編 キャンペーン中/
まとめ
 (画像:暖かい光差す雲取山山頂。竈門一家が炭治郎を送り出す絵が浮かびますね。)
(画像:暖かい光差す雲取山山頂。竈門一家が炭治郎を送り出す絵が浮かびますね。)
さて、今回は秩父エリアにある『鬼滅の刃』の世界観を感じる事ができるスポットを紹介しました。
秩父は『鬼滅の刃』の公式な舞台ではありませんが、作中の背景や時代設定と重なる要素が数多く残されています。聖地巡礼というより、「物語の裏側にある日本の風景と歴史をたどる旅」として、秩父を訪れてみてはいかがでしょうか。鬼滅ファンの皆さんにとって、新たな視点と感動がきっと見つかるはずです。
ただし、いずれも観光地として整備された「映えスポット」ではなく、中にはアクセスに時間がかかる場所や体力を要する登山も含まれます。また、秩父エリアは、今、注目の観光スポットということもあり、大型連休や土日などは、特に混雑が予想されます。そのため、秩父観光をしっかりと満喫するためには、秩父エリアのホテルや旅館での宿泊がオススメです。
鬼滅の世界を楽しんだ後は、パワースポットの寺社巡り・グルメ・温泉・観光スポットで小旅行気分を味わい、秩父を満喫しちゃいましょう!

\ 鬼滅の刃 無限城編 キャンペーン中/